早いうちに資産形成したい。
年齢的にそろそろ家を持ちたい。
という思いからマンション購入を考えはじめたけど
失敗するのが怖い。
大きな金額ですし、そんな気持ちになりますよね。
検討時に考えておきたいことは様々ありますが、今回はその中でも基本的な立地・建物・資金の3つの観点から考えてみます。
新築マンション購入を考え始めたけど、どんな点に注意すればよいか分からない。
後悔しないためにおさえたいポイント
立地

エリア選定
馴染みのある駅、勤務先沿線、憧れの街などエリアを決めるにも様々な選び方があります。
エリア選定は不動産選びの入り口であり、後から変えられないものですので後で後悔してしまうかどうかでは影響度の大きい項目です。
期待する住み心地とのギャップを減らすには基本的には馴染みのあるエリアを選ぶことが望ましいです。
馴染みがあるエリアであれば
- その町のメリット、デメリットが分かっている
- 現在の住環境から変化が少ない
- 想定外の要素が発生しにくい
- 慣れているため、安心感がある
- 親族・知人がいる
などプラス要素が増え、マイナス要素は抑えることができます。
馴染みのない駅で物件を購入することは、一定のリスクが含まれることを理解しておく必要があります。
ただ、独身での購入で長く住むことが前提でなければ利便性・資産性を重視したエリア選定もありだと思います。
もし馴染みのないエリアを選ぶ場合は、
- 勤務先までのアクセス性の確認。
- 利用頻度の高いお店や施設を並べて整理。
- 昼・夜の時間帯も確認(人の多さや街の明るさ)。
は行いましょう。
 tobi
tobi私が独身時代にマンションを購入した時は勤務先の隣駅を選びました!
ミクロ環境
物件地周りの環境です。
気にする要素は
- どんな建物が建っている?
- 将来建物が建ったり、大きな変化がありそう?
- 嫌悪施設はある?
- 騒音はある?
- この場所にはもともと何があった?
これは建設地の確認と物件の営業担当者に聞けばある程度分かります。
検討していく上でのポイントはデメリットのない立地探しをしないことです。
デメリットばかりに目がいってその度に検討を見送ってしまっては、本当に自分に合ったマンションが見つかりにくくなってしまいます。
デメリットはあってもメリットがそれを上回るかを考えましょう。
建物
住戸の広さ・間取り
-4-1024x576.png)
-4-1024x576.png)
国土交通省が定める居住面積水準によると
| 世帯人数 | 都市 | 郊外 |
|---|---|---|
| 1人 | 40㎡ | 55㎡ |
| 2人 | 55㎡ | 75㎡ |
| 3人 | 75㎡ | 100㎡ |
| 4人 | 95㎡ | 125㎡ |
現在の首都圏で販売されている物件と比較すると上記水準は広い印象ですね。
2022年に販売されている間取りをみても狭小化が進んでおり、単身向けは30㎡台、ファミリー向けは60㎡台が主流となっています。
面積自体が狭小であっても、間取りが効率的であれば数㎡程度の差は埋まりますので最終的には面積よりも間取り効率を重視しましょう。
周りの部屋からの音
-5-1024x576.png)
-5-1024x576.png)
上の階に小さなお子様がいらっしゃったりすると音がしないというのは難しいと思います。
基本的に自分でどうにかできるものではありませんが、
- マンション全体の住戸構成を確認する
- 希望住戸の上下左右の面積・間取りを確認する
ことである程度は想定することができます。
マンション全体の住戸構成はモデルルーム見学に行けば、マンション全体の図面がもらえますので確認しておきましょう。



いきなりモデルルームに行くのは不安。
まだ情報収集の段階。
という場合は事前に情報を確認する方法のひとつとして
「SUUMOナビカウンター」や「女性のための快適住まいづくり研究会」が色々と紹介しており、気になるマンションも取り扱いがあれば図面なども含め確認できると思います。
全体の構成と併せて上下やフロアの構成も確認しておきたいですね。
マンションは計画上、縦の系列で同じ間取りが続くことがほとんどです。
ですので、上下階は家族構成が似ることが想定できます。
隣の部屋の面積がどうであるかはマンションによって変わりますので図面をよく確認しておきましょう。
内装・設備
-9-1024x576.png)
-9-1024x576.png)
後から変えることのできない立地などと比較しますと、内装・設備は不動産価値の観点では影響度は少なく、
基本的には
立地・周辺環境>内装・設備
と考えておいた方がよいです。
でも、せっかく新たに住替えるのであれば自分好みの内装のところに住みたい!
好みの部屋じゃないと気持ちが上がらない!
そんな方もいらっしゃるかと思います。
新築物件の場合、青田売り(完成前の販売)であれば無償でフローリングやドアなどのカラーを3パターン程度から選べる物件が多いです。
タイミングはだいたい販売初期から中期程度(竣工する前で部材の発注が間に合う期間)。
パターンは明るい・中間・濃いの3色展開が多いです。
用意されたパターンで満足できない方は、予め自分がやりたいことがいくらくらいかかるものか把握しておきましょう。
住戸位置
- 自分の検討している部屋の正面に何があるのか?
- 日照時間はどうか?
この点は確実に確認されるかと思います。
その他にも住戸位置によって変わるとして
- エントランスまでの距離
- ゴミ置場までの動線
とくに大規模物件ですと様々な動線があり、お部屋によって遠回りとなる可能性があります。
- エレベーターまでの距離
エレベーター近いと人溜まりがあったり、自分の部屋の前を通過する人が増える。
反面、角住戸だと部屋の前を通過するのは自分だけ。
- 共用廊下側にも窓がある間取りの場合、その窓の正面に共用階段(非常階段)が位置しているか?
-2-1024x576.png)
-2-1024x576.png)
共用階段があることでそこに面する洋室が暗くなります。
住戸の位置は当然ながら、毎日の生活への影響が大きいです。
想像を働かせながら、図面の中をよく歩いてみましょう。
共用部
新築マンション購入時に見えにくいのが共用部です。
- 外観
- エントランス
- 内廊下
- 共用施設
代表的な部分はCGを作っている場合があり、まだイメージつきますがその他はどうでしょうか。
- 外廊下の場合、廊下の壁面はタイルか?吹付か?
- バルコニーの手すりの形状は?
- 宅配ボックスの数は?
- 内廊下は空調あり?換気のみ?
細かな部分は営業担当者もあまり説明しない場合があります。
ですが、素材や形状といったところもマンション全体のグレード感に影響しますので確認しておきましょう。
資金
支払いが厳しい


最近は金利も低く、高額なローンを組むケースも多くなってきていますね。
一般的には新築マンション購入の場合年収の7倍程度や、年収に対する支払いの比率が25%以内が目安としてよく言われています。
ただし、頭金の金額、日頃の生活費によって異なるため、目安だけでなく
- 現在の手取り金額
- 現在の家賃
- 現在の支出
から返済額を確認しましょう。
現在で十分な貯蓄の余裕を持てていますでしょうか。
購入した場合はローン返済だけでなく、管理費・修繕積立金・固定資産税等がかかってきますので、それらを含めた上で貯蓄の余裕があることが望ましいです。
資金関連での失敗を防ぐには、ファイナンシャルプランナーに細かい支出も含めた生涯のシュミレーションを出しておくのが望ましいです。
検討している新築マンションのモデルルームでもファイナンシャルプランナーとの無料相談をやっていることが多いですのでやって損はないと思います。
ただし、モデルルームで紹介されるファイナンシャルプランナーは当然ながらマンションの販売会社とつながっておりますので多少は無理はあっても購入を進める方向で案内される場合があります。
そこは鵜吞みにせず、しっかりと自分自身で判断するようにしましょう。
住んでしばらく経ってからかかる費用も想定しておく
固定資産税等も含めておくのはもちろんですが、検討時に見逃しやすい下記項目もしっかり考えておきましょう。
①修繕積立金
-7-1024x576.png)
-7-1024x576.png)
共用部を補修していくための費用で、修繕積立金は基本的に上がっていきます。
これは、年数が経てば経つほど修繕すべき箇所は増えていくためです。
何年ごとかは管理会社によってことなりますが、一気に倍近くということもありますのでよく確認しておきましょう。
これはマンションの販売会社に
修繕積立金は上がっていきますか?
長期修繕計画を確認させてもらえますか?
と聞けば確認することができます。
②修繕積立基金
まとまった修繕積立金とイメージしていただければと思います。
修繕積立基金がかかるかは管理会社によります。
かかる場合は概ね10年ごと程度が多い印象です。
広さによって金額は異なりますが30万円程度はかかってくると思います。
③室内の維持・管理
修繕積立金は共用部の修理となりますが、自分のお部屋内はもちろん自身で維持・管理していかなければなりません。
10年も住めばどこかしら直すべき箇所が出てくると思います。
あくまでも目安ですが、
新築から10年で50万円程度は想定しておきましょう。
例えば給湯器が交換となると30万円以上はかかってきます。
おわりに
これまでをまとめますと
- 馴染みの深いエリアで選ぶ。通勤軸で広げるのはOK。
- マイナス点ばかり見ず、それを上回るメリットがあるかを考える。
- 設備や内装などよりも基本的には立地優先
- 部屋までの動線など、EVの位置など共用部の位置関係をよく確認する
- 部屋の中だけでなく、共用部の仕様も確認する
- ローン返済額の他、管理費・修繕積立金・固定資産税も含めて貯蓄ができる設定にする。
- さらに先の修繕積立金の上昇、修繕積立基金、設備の修繕費も想定しておく。
このあたりはしっかりチェックしておくことで、少しでも住んだ後のギャップを減らしていきましょう!
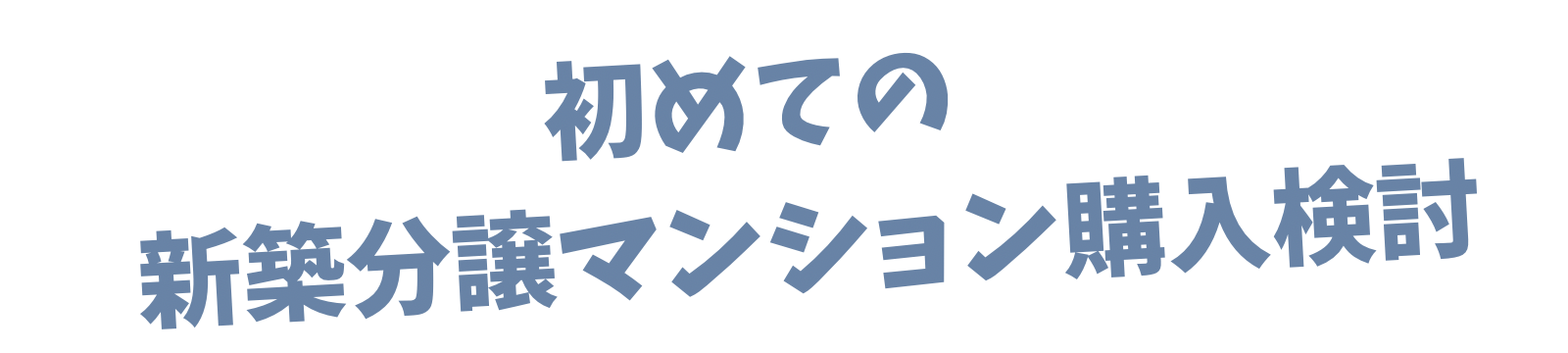




コメント